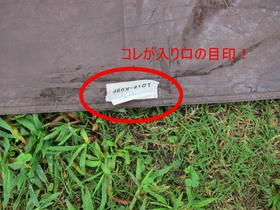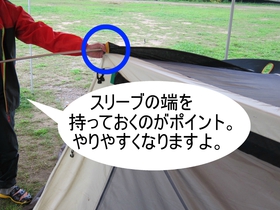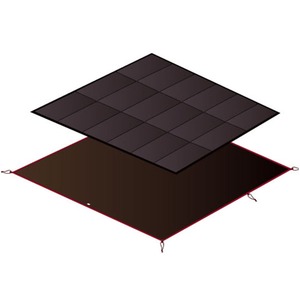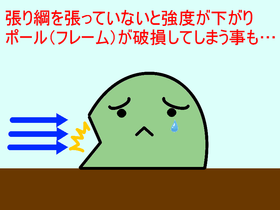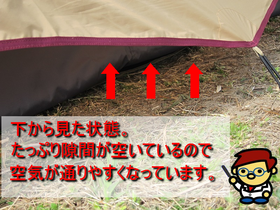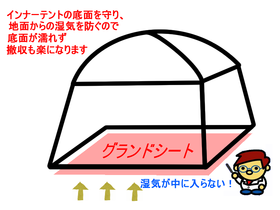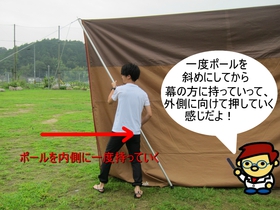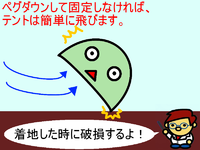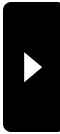2018年01月29日
【スノーピーク】アメニティドームの立て方
アメニティドームを立てよう!
一度は使ってみたい、憧れの商品ではないでしょうか?
でも、説明書を読むと、パーツが多そうで難しいんじゃないかな…
と思われている方も多いのではないでしょうか。
そこで、アメニティドームの立て方を掲載致しました。
どうぞご活用下さい。
なお、張り綱はテントに結びつける必要があります。
こうした場合は、【もやい結び】がおススメです。
結び方は、下記でご紹介しておりますのでご参照くださいませ。
【もやい結び】

テントを立てる前に、内用品が全て入っているか確認をしましょう!
セット内容:インナ×1、フライシート×1、本体フレーム×3、前室フレーム×1
ジュラペグ(17cm×16)、自在付きロープ(2.5m×2本、二又用1.9m×2本、二又用1.4m×2本、0.7m×4本)
リペアパイプ×1、キャリーバッグ×1、フレームケース×1、ペグケース×1、
※グランドシート、フロアマット、ハンマーは付属していません。
この時、入り口側が風下に来るようにしておきましょう。
入り口の目印は、白いタグが縫い付けられている部分です。
※グランドシートは別売です。セットに含まれていません。
グランドシートは、インナーテントの組立てが終わってから位置を決めて設置して下さい。
この時、ビルディングテープ(黒いテープ)が付いている方が、テントの入り口になります。
グランドシートの白いタグと合わせるようにしましょう。
フレームを通す時は、引っ張らず、押していくように入れます。
両方とも通していきましょう。
フレームを上に持ち上げず、スリーブが真ん中に来るように調整しながら、寝かせた状態で曲げて、ピンに刺しましょう。
反対(左前)側のスリーブの端を持ちながら、フレームを押し込んでいくとテントが立ち上がります。
立ち上がったら、フレームをピンに差し込みます。
入り口左側にはピンが2つありますが、向かって左側の方(奥の方)に差し込みましょう。
風がキツイ場合は、テントが飛ばされないよう、反対側でもう一人がテントを抑えておきましょう。
- ピンの位置を間違わないようにしましょう
これを緑色テープのスリーブに通していきます。
黄色テープのポールの上を通るようにしておきましょう。
これをフレームにかけていき、ポールとインナーテントを固定します。
黄色テープのフレームと、緑テープのフレームが交差している部分は、下のポールを挟みこむような感じで取り付けます。
これでインナーテントは完了です。
赤い三角の部分がベンチレーションですので、これが後側の目印です。
向きを確認してから、インナーテントに被せます。

- 向きを間違えないようにしましょう!

- ポールとフライシートが合うように設計されています
この時もスリーブの端を持ち、フレームを引っ張らずに、押し込むようにして入れていってください。
もう片方は、黒いビルディングテープについているピンに差し込みます。
同じ色同士になっているか確認しましょう。
まずは寝室(インナーテント)がある部分からペグダウンしていきましょう。
1.インナーテント前面の右角 ※グランドシートのループも一緒にペグダウン。
2.対角線上の、インナーテント左後ろ(角を引っ張りながらペグダウン)
3.インナーテント右後ろ
4.インナーテント前面の左角 (角を引張りながらペグダウン) 5.サイド右側(緑のテープのところ) 6.サイド左側(緑のテープのところ)
前室の右側に張綱(二又用1.9m)を取り付け、前室が広がるように引っ張りながら、調整してペグダウンします。
前室左側も張綱を取り付け、引っ張りながら、調整してペグダウンします。
其々、ループが二つありますが、入り口になる部分(内側の部分)はペグダウンしないように気をつけましょう。
サイドの張り綱は、グレーの三角形の真ん中ぐらいにロープが来るようにすると綺麗です。
張り終わったら、ビルディングテープのバックルを外して、ビルディングテープをテープポケットに入れておきましょう。
使用したアイテム
キャンプ場は地面がゴツゴツしてますし、朝晩の冷え込みもございます。
テントの保護や、湿気・冷気防止の為には、グラウンドシートが欲しいところですね。
地面のゴツゴツの緩和には、フロアーシートがあると、より快適に過ごせます。
- フロアーマットで更に居住性を高めましょう
2017年12月14日
【アウトドア】基本のロープワーク
基本のロープワーク(もやい結び、自在結び)
普通に結ぶだけでは解けてきて危ないし、固結びをすると、今度は解く時に大変…そんな経験をされた方も多いかと思います。
そこで、今回はキャンプの際の基本のロープワーク
「もやい結び」と、「自在結び」についてご説明します。
「もやい結び」は、簡単に結べて、負荷がかかっても解けにくく、且つ、手で解くと簡単に解ける、アウトドアでの基本のロープワークです。
「自在結び」は、自在金具が破損してしまったり、失くしてしまった際に役立ちます。
どちらも、テントやタープを張る際に必要となりますので、この機会にしっかり覚えて、フィールドで役立ててくださいませ。
また、既にご存知のお客様もいらっしゃると思いますが、復習に役立てて頂ければ幸いです。
★結び方★
もやい結び
自在結び
□
□
もやい結び
コツをつかめば片手でも結ぶことが出来ます。
強い力がかかった後でも解くことが容易です。
テントやタープを立てる際に使用する、必須の結び方です。
□
□
自在結び
ロープの長さを変えて、テンションをかけることが出来るので、自在が無い時などに役立ちます。
滑りやすい材質のロープや、細いロープの場合、うまく自在が効かない場合があります。
この時、初めの結び目と間隔をあけるようにしてください。
この感覚が、ロープの長さ調整の際の遊びになります。

- 印の部分を手で持ってください。
2017年07月11日
【テント全般】ペグダウンと張り綱の重要性
実は、テントは風の影響を非常に受けやすい物となっています。
ペグダウンをせず、張り綱を張っていない場合、テントが飛んでいってしまったり、ポールが折れたり、曲がってしまう事もあります。
また、誤った方向へのペグダウンや張り綱は、余計な力がポール(フレーム)にかかり、破損の原因となってしまう事があります。
そこで今回は『ペグダウンと張り綱の重要性』及び、『正しいペグダウン、張り綱の方向』について、ご案内させて頂きます。
ペグダウンや張り綱は何の為の物?
・テントを固定する。
・風から受ける力の影響を分散(補強)する。
・ダブルウォール仕様の場合は、フライシートとテント本体の間に隙間を作る。
(ベンチレーション機能が正常に働く)
では、ペグ、張り綱を使っていない場合、具体的にどのような事が起きるのでしょうか?
「テントの中に荷物を置いておけば、固定される、飛んで行くことはない」
そう思われていらっしゃる方は居ませんか?
残念ながら、そんな事はありません。
テントは風の影響を非常に受けやすく、想像よりもはるかに飛びやすいのです。
テントに荷物を入れていても、ペグや張り綱を使っていないテントは簡単に吹き飛ばされます。
飛ばされたテントは、着地した際に布地が破れてしまったり、フレームが折れる事があります。

テントは意外と飛びやすい!
テントが飛ばなくても、風で押されて動く事があります。
地面には棘や石がある為、インナーテントの底面がこすれて破れてしまう事もあります。

引きずられた際にインナーテント底面が破れる事があります。
風から受ける力が分散できず、局所的に力がかかってしまい、ポール(フレーム)が折れたり、曲がったりする事があります。
また、張り綱を正しい方向へ張っていない場合も、同様にポール(フレーム)の破損原因となります。
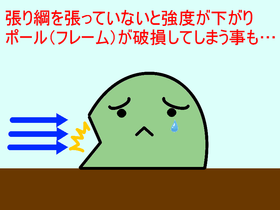
局所に負荷がかかり、破損の原因になります。
ベンチレーション(換気)機能は、フライシートとテント本体の間に隙間が出来る事で、最大限に発揮されます。
ペグダウンや張り綱をしないと、隙間が出来ず、ベンチレーション(換気)機能が働かない為、結露の原因にもなります。
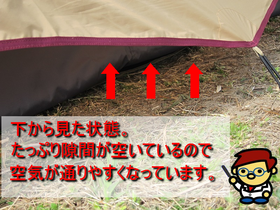
ペグダウン、張り綱を張らないと、フライシートとインナーテントの間に隙間が空きません。
正しいペグダウン、張り綱の方向について
誤った方法、方向へのペグダウン、張り綱では、テントの持つ機能が十分に発揮されません。
また、テントを張る際には、風向きにも注意する必要があります。
テントの固定は、下記の手順で行いましょう。
入り口は、必ず「風下」にします。
入り口が「風上」にあると、テントの中に風が吹き込んでしまい、内部にゴミや砂が入ったり、テントが吹き飛ぶ原因になります。

グランドシートにも入口の目印が付けられているものがあります。
(写真のグランドシートでは、白いタグが入り口側の目印です。)
グランドシートを敷く段階で、入口を決めておきましょう。
まずは風上側の片方にペグを打ち込み、次に対角線上の反対側に打っていきましょう。
スノーピーク アメニティドームの場合は、下記の記事をご参照下さい。
【スノーピーク】アメニティドームの立て方
下に記載する図と説明書をご参照ください。
基本的には、まず地面に近い場所からペグダウンし、その後に張り綱を張るという順番で進めます。
張り綱の張り方は、次の③の項目をご参照ください。
入り口を開けた状態でペグダウンすると、後でファスナーが閉まらなくなる事があります。

メーカー、製品によって、ペグダウン位置が異なる為、必ず説明書をご確認下さい。

先に張り綱を張らないようにしてください。

ペグの角度にも注意。
地面に対して60度~90度の角度に傾けます。

- ペグはしっかり打ち込みましょう!
フレーム位置にある張り綱は、フレームの延長線上にある位置の地面に固定してください。
フレームの延長線と極端に違う方向に張り綱を引っ張ると、不必要な力がフレームに働き、フレーム破損の原因になります。
また、張り綱は必ず、地面に固定して下さい。
立ち木等、地面よりも高い位置に張り綱を固定すると、テントにかかる力が分散されてしまい、強度が落ちてしまいます。

張り綱がピンと張るように、自在などで調整して下さい。
テントの性能を最大限発揮する為、張り綱は全て張りましょう!
2017年04月25日
【テント全般】重ね敷き(テントレイヤード)の重要性
そういったお問い合わせを頂く事が多くございます。
ペグ等は勿論なのですが、意外と忘れられがちな物があります。
それは「グランドシート」や「フロアマット」、「エアマット」です。
『テントで寝ると、ゴツゴツして寝づらい…』そんな経験はありませんか?
また、テントの保護は勿論の事、他にも、機能がある事はご存知でしょうか?
今回は、重ね敷き(テントレイヤード)について、ご案内致します。
重ね敷き(テントレイヤード)とは?
その対策として、グランドシートやフロアマット、エアマット等を重ねて敷き、床面の保護、凸凹や湿気の緩和を行うことを、「重ね敷き(テントレイヤード)」と言います。
重ね敷き(テントレイヤード)を取り入れることで、地面の凹凸や底冷え、湿気をやわらげ、より快適な空間を作り出す事が出来ます。
・地面の凸凹の影響を受けやすく、テント底面が傷つく。
※酷い場合には、穴が開いたり、破れたりします
・地面からの湿気や冷気の影響を受けやすくなり、テント内部に『結露』が発生する。
※湿度の高い日や草地、雨天時は、テント内部に結露で水溜りが出来てしまいます
・地面の湿気の影響をそのまま受ける為、テント底面が濡れてしまう。
このようなトラブルを回避する手段が、重ね敷き(テントレイヤード)です。
重ね敷き(テントレイヤード)をしてみよう
そもそも、テントは、フィールドにおける「家」のような物。
地面に直にインナーテント(家)を建てて、フライシート(屋根)をつける…
…こう考えると、何か足りないな、と思いませんか?
家を建てるには、「基礎や土台」が必要です。
その基礎や土台の部分になるのが、「グランドシート」です。
「グランドシート」は、テント底面の保護に加え、地面からの湿気や冷気を防ぐ効果があります。
底面の破損や結露等のトラブルを回避、緩和する為にも、必ずグランドシートを引いて頂く事をお勧め致します。
【グランドシートがある場合のメリット】
・テントが地面に直接触れないので、テント底面が傷ついたり、汚れる事を防げます。
・地面からの湿気を緩和するので、テント底面が濡れる事を防げます。
・テント内部に結露が発生しにくくなります。
・メーカー純正品が一番ぴったりで、おススメです。
・純正品がない場合には、インナーテントの底面よりも少し小さめの物を選んで下さい。

- グランドシートが無い状態。
地面に直接、テント底面が接するので、底面の破損や汚損が発生します。
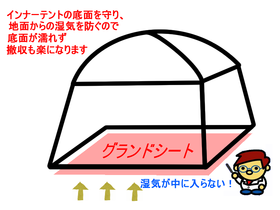
- グランドシートがボトム(インナーテントの底)からはみ出ない様に敷きましょう。
はみ出ると、フライシート(屋根)から流れ落ちた雨水がグランドシートに溜まり、浸水してしまう恐れがあります。




- こちらはインナーテントに合ったサイズを選んで下さい。



- インナーテントも含めて四重構造になるので、冷気が更に伝わりにくくなり、地面の凸凹も気になりません。



- 地面の凸凹や冷気、湿気が伝わらない上、ベッド感覚で休めます。
グランドシート、フロアマット(インナーマット)との併用を推奨します。
※冬場は、コットの上にインフレータブルマットを敷くと背面の冷気を防ぐ事が出来ます。 
- ベンチや荷物置きとしても使えます。
但し一点に荷重が集中する為、ベンチ利用は短時間にてお願いします。
グランドシート(基礎)の上にテント(家)を建てたら、次に何が必要になるでしょうか?
フローリングの床を思い浮かべてみて下さい。
そのままだと、ヒンヤリして、冷たいですよね。
「畳や、カーペットが欲しいな」と思いませんか?
その畳や、カーペットの役割を果たすのが、フロアマット(インナーマット)です。
グランドシートでは防ぎきれない、地面の凸凹や湿気、冷気を緩和する役割があります。
テント内部の『結露』を防ぐのに、より効果的ですし、テント内部が更に快適になるので、お勧めです。
【フロアマット(インナーマット)がある場合のメリット】
・グランドシートで防ぎきれない、地面の凸凹が緩和されます。
・地面からの冷気や湿気を緩和するので、足元が冷たくなりにくいです。
・更に、テント内部に結露が発生しにくくなります。
・メーカー純正品が一番ぴったりで、おススメです。
・純正品がない場合には、インナーテントに合ったサイズをお選び下さい。
カーペットを敷いた事で、ずいぶんとテント内部が快適になりました。
このまま、シュラフ(寝袋)に入って寝てしまいたくなります…
ですが、ご自宅でお休みになる場合は、ベッドや、敷布団をご利用頂いていますよね?
ベッド、敷布団の役割を果たすのが「インフレータブルマット」や、「エアマット」です。
インフレータブルマット、エアマット、エアベッド、アルミマット等を活用すると、より快適な睡眠を得る事ができます。
【マットがある場合のメリット】
・より高い防寒性とクッション性が得られます。
・地面の凸凹が殆ど気にならないので、より快適にお休み頂けます。
フロアマット(インナーマット)はあくまでも「カーペット」的な役割なので、薄手になっています。
地面の凸凹を緩和できますが、更に快適な睡眠を得る為に、マット(敷布団)を用意しましょう。
番外編 コットを使ってみる
そんな方におススメなのが、「コット」です。
キャンプ用の簡易ベッドと考えて下さいませ。
・テントの外でお昼寝する時にも使えます。
・地面から離れた状態になり通気性が良いので、夏場などの暖かい時期にもお勧めです。
もしシュラフが薄手で寒いようであれば、フリースインナーをシュラフの中に入れる等をお試し下さい。
アウトドアライフを、より楽しく、快適にお過ごし頂ければ幸いです。
2016年10月20日
【テントファクトリー】4シーズンダブルドームテントの立て方
4シーズンダブルドームテントを立てよう!

他のテントには無い圧倒的なサイズ感のあるテントとして、発売開始以降、大変ご好評頂いております。
しかしながら大きい為、立てるのに苦戦したとのお声も頂いております。
そこで、今回は4シーズンダブルドームテントの立て方を掲載致しました。
どうぞご活用下さい。
なお、ガイドロープ(張り綱)はテントに結びつける必要があります。
こうした場合は、【もやい結び】がおススメです。
結び方は、下記でご紹介しておりますのでご参照くださいませ。
【もやい結び】
3人以上で設営を行うと、比較的に楽に設営ができます。
4シーズンダブルドームテントの立て方
設営は必ず2人~3人以上でおこなってください。
3人以上で設営を行うと、比較的に楽に設営ができます。
※1人で設営した場合、ポールに無理な力がかかり、破損する危険性がございます。
ポールの差し込み方にご注意ください。
テント本体が大きいため、ポールの差し込みを誤ると、重量がかかり折れの原因になる場合がございます。
テントを立てる前に、内用品が全て入っているか確認をしましょう!

- 【4シーズンダブルドームテント】
セット内容
■インナーテント×1
■フライシート×1
■メインポール(黒色)×4
■フロントポール(白色)×1
■キャノピーポール(グレー)×2
■ペグ
■ガイドロープ
■プラスチックハンマー×1
TENT FACTORYの文字がある方が、前室になります。
こちら側(入り口側)が風下に来るように広げてください。
方向を間違わないようにしましょう。
ポールを入れる順番は特にございません。
この時、ポールを連結させながら、引っ張らず、押していくようにして入れてください。
スリーブの端部分を持った状態で入れると、スムーズにポールを通す事ができます。

ポールを押しながら入れるのがポイント。
引っ張ると連結部が外れ、フライシートが嚙み込んで、破損に繋がる事があります。
テントを立ち上げる時は、2人~3人以上で行ってください。

テントの上部を持ちあげると、立ち上げが比較的楽に出来ます。

2人~3人で立てるようにしてください。
3人以上であれば、よりスムーズに立ち上げられます。

一人で立ち上げた場合、写真の様に、ポールに極端な曲がりが発生し、破損の原因になる事がございます。

ポールの先端をグロメットに差し込む際、場所を間違わないようにして下さい。

- 写真のように、ポールがクロスした状態が正しい位置になります。

ポールを間違ったグロメットに差し込んだ状態。
ポールに強い曲がりの負荷がかかり、破損の原因になります。
メインポールと同様に、スリーブの端部分を持った状態で、ポールを連結させながら、引っ張らず、押していくようにして入れます。
前室部分にリングがありますので、ポールを通し、ポール先端をグロメットに差し込んで固定します。
フレーム交差部はベルトで固定します。
グランドシートにはフックが付いており、フライシートに固定できるようになっています。
下部はバックルで固定して完了です。
テントインナーマットがある場合は、インナーテントの内部に敷いて下さい。
2016年01月04日
【oxelo(オクセロ)】TOWN7サスペンションの畳み方
TOWN7サスペンションの折り畳み方、組立て方
でも、TOWN9と少し畳み方が違うので、『上手く畳めない…』とお悩みのお客様も多いようです。
そこで、今回は、【TOWN7サスペンション】の畳み方をご説明いたします。
また、組み立て方がよく分からないというお声も頂いております為、組み立て方についてもご説明いたします。
折り畳み方
本体部分(ハンドル側)にも、畳み方が記載されています。

- このネジが緩んでいないと、畳みにくい事があります。
この時、ハンドルを押していないと、黒いレバーが倒れませんので、注意しましょう。
カチッと音がするまで押して下さい。
組立て方
この時、ネジが緩んでいるようならば、締めなおしておいてください。

ストッパーは必ず確認して下さい
高さは、3段階で調節できます。
調整が終わったら、ハンドルロックを締めます。

ボタンロックが穴から出ていない場合、走行中にハンドルが下がり、大変危険です。

ボタンロックが穴から出ている事を確認してから、ハンドルロックを締めて下さい。
こちらも、ボタンロック式になっていますので、ボタンロックが、穴の部分にちゃんとはまる様にしてください。
他シリーズについては、畳み方が異なりますので、ご注意下さい。
2015年09月24日
【スノーピーク】アメニティドームのたたみ方
アメニティドームのたたみ方
でも、テント本体が四角形ではないので、たたみ方がよく分からないですよね。
手順をご説明いたしますので、参考にしてみてください。
フライシートをたたむ
サイドの、灰色の三角形の頂点が隠れるぐらいが丁度いい目安です。
先ほどたたんだ前室に被せるようにたたんで下さい。
軽く押しながら、巻くようにしてたたんでいきます。
インナーテントをたたむ
※閉めたままだと、中に空気が残り、収納がしにくくなります。
※真ん中が【タニ折り】になる感じです。
ケースに収納する時は、次に使用する時の順番を考えます。
フライシート⇒インナーテント⇒フレーム、ペグ の順番で収納していきましょう。
雨の日はどうする?
手順をご説明いたしますので、参考にしてみてください。
ポールは、真ん中の方から折り畳むようにして下さい。
端から折っていくと、ポールの中のショックコードにテンションがかかりすぎて、ショックコードが切れる原因となります。
ポールは、真ん中の方から折り畳むようにして下さい。

- グランドシートがある場合は、こちらも同じく軽くたたみ、ビニール袋に入れてください。
テントが濡れたままだと、カビが生えてしまいます。
一旦家に持ち帰った後、干して乾かしましょう!
2015年09月15日
【スノーピーク】ヘキサタープの立て方
ヘキサタープを張ってみよう!
でも、立て方がよく分からなくて、躊躇してしまいますよね。
そこで、初めての方でも立てやすい方法を掲載致しました。
どうぞご活用下さい。
なお、ポールにロープを引っ掛ける際、ループ(輪っか)を作る必要があります。 こうした場合は、【もやい結び】がおススメです。
【もやい結び】は、幕体にロープを結ぶ際にも使用いたします。 結び方は、下記でご紹介しておりますのでご参照くださいませ。
【もやい結び】
なるべく、一人で立てず、二人以上で協力して立てるようにして下さい。
タープを立てる前に、内用品が全て入っているか確認をしましょう!
セット内容:タープ本体、ウイングポール(280cm、240cm)
ソリッドステーク40(×4)、ソリッドステーク30(×4)、自在付ロープ(ニ又用10m×2、3m×2、2m×2)、
ぺグハンマーPro.C、ポールケース、ロープケース、ぺグ&ハンマーケース、キャリーバッグ
※上記はProセットの内容品です。
設置箇所が決まったら、幕体が風で飛ばされないように、折り目の部分のループを軽くペグダウンして、仮止めしておきます。
ポールを、折り目の直線上に置きます。

- ※ 240cmのポールを使用します。
写真はレクタタープの物ですが、手順は同じです。
直角二等辺三角形の頂点の部分(丸の部分)にペグを打ち込みます。
二又のロープを使用しますので、逆方向にも倒して、ペグを打ち込みます。
この時、しっかりペグを打ち込みましょう。
幕が長いほうに280cmのポールを、短い方に240cmのポールを差し込んでください。
自在ロープ(2又9mの方)の頂点を幕の上からポールに引っ掛けます。
※両サイドとも、同じ様にします。
引っ掛けたら、テンション調整をします。
ロープを持ち上げてみて、腰の高さぐらいでピン!と張るぐらいが丁度良い目安です。

- これぐらいが良い感じ。
この時、外側から内側へ押し込んで立てようとしがちです。
無理に中に押し込もうとすると、ポールが曲がったり折れたりします。
その為、一旦ポールを幕の内側へ斜めに持っていき、内側から、外に押すようにしていきます。
こうすると、力を入れなくてもポールが立ちやすくなります。

- ヘキサタープの場合は、少し内側にポールの根元を持っていくようにします。
※既に自立している側のポールが不安定になることがありますので、もう一人が支えておいてください。
先ほどと同様に、内側から外側へ押すように、ポールを立てていきます。

- ポールの根元が少し内側に入るように立てます。
真ん中が少しだけ、たわむ様にすると、綺麗なカーブが出来ます
この時、自在ロープ、ペグ、ペグハンマーを一緒に持っておきましょう。
四隅のグロメットの一つに、付属の自在ロープを「もやい結び」で取り付けます。
【もやい結び】
対角線上のほうも同じ様にペグダウンします。

- グロメットの方向に真っ直ぐロープを引っ張りましょう。
ロープの位置が、図の様に四角形になるように張っていくと、綺麗に張れます。
4箇所全てペグダウンし、テンション調整をしたら完了です。

- メインポール側の長方形、サイドロープ側も長方形の位置になるようにします。

- 出来上がりイメージ
使用したアイテム
セットでない物には、ポール、ペグ、ハンマー、ペグ&ハンマーケースは含まれておりません。
ご注意下さい。
2015年09月15日
【スノーピーク】レクタタープの立て方
レクタタープを張ってみよう!
でも、立て方がよく分からなくて、躊躇してしまいますよね。
そこで、初めての方でも立てやすい方法を掲載致しました。
どうぞご活用下さい。
なお、ポールにロープを引っ掛ける際、ループ(輪っか)を作る必要があります。 こうした場合は、【もやい結び】がおススメです。
【もやい結び】は、幕体にロープを結ぶ際にも使用いたします。 結び方は、下記でご紹介しておりますのでご参照くださいませ。
【もやい結び】
なるべく、一人で立てず、二人以上で協力して立てるようにして下さい。
タープを立てる前に、内用品が全て入っているか確認をしましょう!
セット内容:タープ本体、ウイングポール(280cm×2)
アルミポール(170cm×4)、ソリッドステーク40(×4)、ソリッドステーク30(×4)、ジュラピンペグ(×4)
自在付ロープ(二又用10m×2、3m×8)、ぺグハンマーPro.C、ポールケース、ロープケース
ぺグ&ハンマーケース、キャリーバッグ
※上記はProセットの内容品です。
設置箇所が決まったら、幕体が風で飛ばされないように、折り目の部分のループを軽くペグダウンして、仮止めしておきます。
ポールを、折り目の直線上に置きます。
※太いポールを使用します。
直角二等辺三角形の頂点の部分(丸の部分)にペグを打ち込みます。
この部分には、二又ロープを使いますので、逆方向にも倒して、ペグを打ち込みます。
この時、しっかりペグを打ち込みましょう。
自在ロープ(2又9mの方)の頂点を幕の上からポールに引っ掛けます。
※両サイドとも、同じ様にします。
引っ掛けたら、テンション調整をします。
ロープを持ち上げてみて、腰の高さぐらいでピン!と張るぐらいが丁度良い目安です。

- これぐらいが良い感じ。
この時、外側から内側へ押し込んで立てようとしがちです。
無理に中に押し込もうとすると、ポールが曲がったり折れたりします。
その為、一旦ポールを幕の内側へ斜めに持っていき、内側から、外に押すようにしていきます。
こうすると、力を入れなくてもポールが立ちやすくなります。
※既に自立している側のポールが不安定になることがありますので、もう一人が支えておいてください。
先ほどと同様に、内側から外側へ押すように、ポールを立てていきます。
この時、ポールと、自在ロープ、ペグ、ペグハンマーを一緒に持っておきましょう。
四隅のグロメットの一つに、細いポールを差し込み、付属の自在ロープを幕の上からポールに引っ掛けます。
細いポールが立ったら、今度は対角線上のほうも同じ様にポールを立ててペグダウンします。
4箇所全てペグダウンしたら完了です。
使用したアイテム
セットでない物には、ポール、ペグ、ハンマー、ペグ&ハンマーケースは含まれておりません。
ご注意下さい。
ナチュラム君のワンポイント講座!
参考にしてみてくださいね!
ナチュラム君の、雨の日ワンポイントアドバイス!

- 別売のロープ、ペグをご利用下さい。
2015年08月05日
【ペトロマックス】ランタンの点け方
ペトロマックスランタンの点火方法
ペトロマックス社の加圧式ランタンは、プレヒート(予熱)が必要となり、ガソリンランタンとは使用方法が異なります。
また、空気圧ゲージが付いており、ポンピングはゲージを目安にして行います。
しっかり使い方を覚えて下さいね。
灯油に比べ、ガソリンは引火点が低い為、事故の元になります。
手順
タンク七分目ぐらいが目安です。
HK150は0.38Lぐらい
HK500は1Lぐらいです。
規定量以上は、絶対に入れないで下さい。
グリップホイールの矢印が上向きになっている事を確認して下さい。
露出したインナーチムニー下部にマントルを取り付け、糸を引っ張り、固定します。
この時、マントルへの接触を防ぐ為、余分な糸は切っておいてください。
ポンピングしてタンク内の圧力を上げていきます。
目安は2.0kg/qcm程度(真ん中の、赤い線が目印です)までです。
赤い目印の線を越えないようにしてください。
あまり圧力をかけ過ぎると点火時にマントルが破けてしまいます。
余熱バーナーを開いて、チャッカマン等で素早く着火すると予熱バーナーが勢いよく燃焼します。
マントルに火がついたら、一旦余熱レバーを戻します。
カラヤキが終わったら、再度余熱レバーを開き、着火して2分ほど、しっかりプレヒート(予熱)を行ってください。
なお、この時も圧力が消費されるので、必要に応じて追加ポンピングをしましょう。

- 圧力が下がったらポンピング!
一気に回転すると、内部圧力が急に高くなり、マントルが破けてしまうことがあります。
余熱バーナーは、点火後に締めてださい。
なお、この段階で、ランタンが炎上するような場合は、プレヒート不足です。
直ぐに圧力調整ねじを緩めて、プレヒートからやり直してください。
- 「ポッ」という音とともに、マントルに火が移ります
圧力が抜けて、ゆっくりと火が消えていきます。
使用後は、タンク内の燃料を抜き取って下さい。
使用したアイテム

故障かな?と思ったらこちら